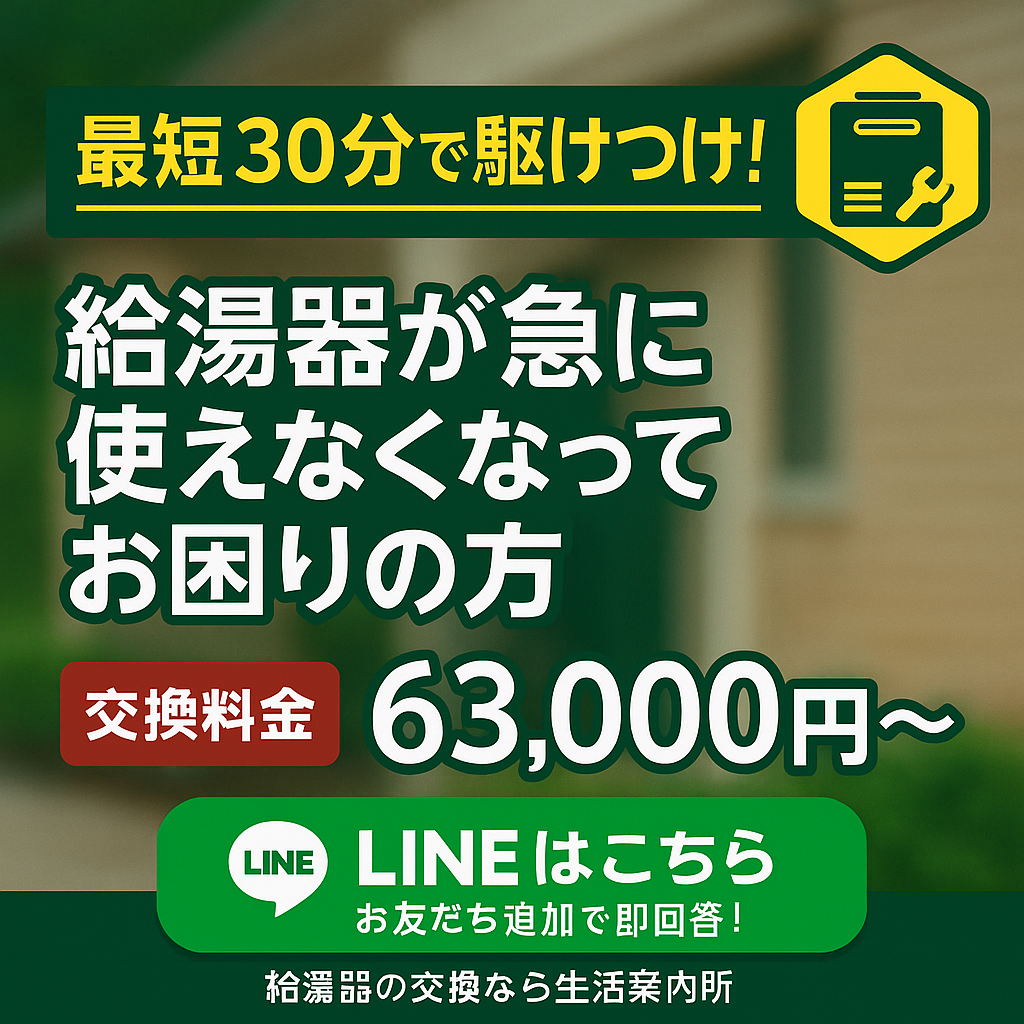給湯器交換歴25年、年間施工件数2,000件以上の実績を持つ全国担当マネージャー大塚が、このページの解説を担当します。暖房給湯器やエコキュートはもちろん、ガスコンロ、浴室暖房乾燥機まで全機種対応。給湯器のトラブルは、技術と経験が豊富なプロにご相談ください。

マンションの給湯器交換は、戸建てとは異なる複数の壁が存在します。特に交換費用を誰が負担するのかという問題は、分譲と賃貸、それぞれの契約や規約によって判断が複雑化します。急にお湯が出なくなる不安に加え、予想外の出費や、管理組合との調整、賃貸契約上の責任といった特有の問題が重くのしかかります。単に費用相場を知るだけではトラブルは回避できません。
最も重要なのは、ご自宅の給湯器が法的に「誰の所有物」と見なされ、「誰が修繕責任を負うのか」を正しく理解することです。特に東京都心やその近郊の集合住宅で多く見られるPS(パイプスペース)設置型は、その境界線が複雑になりがちです。当ページでは、あなたが賃貸・分譲どちらの立場であっても、費用負担を最小限に抑え、最短で新しいお湯のある生活を取り戻すための具体的な手順を解説します。実際の民法の根拠や管理組合への交渉術、そして明日から使える最終手段まで、実務的なノウハウをお伝えします。専門的な知識に基づき、マンション給湯器の交換における交換費用の責任の所在を明確化し、管理組合や大家とのトラブルを未然に防ぐための道筋を示します。
「専有部分」と「共用部分」の境界線マップで責任の所在を3秒で判定
給湯器の交換費用は、機器が専有部分か共用部分かによって負担者が確定します。特にPS(パイプスペース)設置型は境界が複雑なため、管理規約や賃貸契約書を正確に読み解く必要があります。最初に責任の所在を3秒で判断できれば、その後の大家や管理組合との交渉トラブルを未然に防げます。
マンション給湯器の交換費用を誰が負担するかは、その機器が「専有部分」か「共用部分」かによって法的な責任が分かれます。まず、ご自宅の給湯器がどちらに該当するかを判断することが、費用負担の問題を解決する最初のステップです。特に配管や給湯器本体がパイプスペース(PS)内に設置されているケースは、判断基準が曖昧になりがちです。この初期の判断ミスが、後の管理組合や大家とのトラブルに発展する主な原因となります。自己判断で業者を手配する前に、正しい境界線を把握しましょう。
PS設置型の給湯器本体は誰のもの?分譲マンションの規約の読み方
PS設置型の給湯器本体は、原則として専有部分として扱われます。したがって、機器本体の交換費用は区分所有者(オーナー)の負担となるのが一般的です。分譲マンションの管理規約は、機器本体や専有部分内の給水・給湯管を「専有使用部分」と定めている場合が多いからです。しかし、費用の負担責任は設置場所の構造によって「誰が、どこまで」の責任を明確に区別しなければなりません。給湯器の排気口や給気口、さらには外壁を貫通している配管部分自体は、外観や建物の構造上の理由から共用部分に該当します。この共用部分の改変や修理には、管理組合の承認が必要です。
国土交通省の「標準管理規約」では、給湯器の配管の起点を境界としています。具体的には、パイプスペース内のメーターボックス部分までは共用と見なされ、そこから各住戸に入る部分以降を専有とする規約が多数派です。機器の故障がPSの扉や共用部分の配管の劣化など「共用部分」に起因する場合、その修理交換費用は管理組合の負担となります。重要な注意として、規約に本体交換の明記がない場合でも、後継機種のサイズ変更によりPS扉の加工や排気位置の変更が必要となる場合は、共用部分の改変となるため、管理組合の承認申請が必須です。まずは規約の「専用使用権の範囲」や「給排水設備の定義」の章をチェックし、給湯器のサイズ変更が必要かどうかの判断材料にしましょう。この初期判断が、後の大規模なトラブルの防止に直結します。

分譲マンションにおける給湯器交換費用の負担は、機器の所有権ではなく「規約による修繕責任の範囲」で確認することが最も実務的です。機器交換は専有部分の設備の更新ですが、PSという管理組合が管理する共用部分に設置されている特殊性を理解する必要があります。工事に伴う共用部分への影響を最小限に抑え、所有者が交換費用を負担し、管理組合への事前の申請を行うことが、スムーズな交換の絶対条件です。
賃貸契約書に「入居者負担」とあっても交渉で覆せる「民法の根拠」
賃貸契約書に「給湯器の修理・交換費用は入居者負担」と記載されていても、民法の規定によりその条項を覆せる可能性が極めて高いです。この民法の根拠を知ることが、入居者が不当な費用請求から身を守るための最大の武器となります。法律の原則は「設備の修繕義務は貸主にある」という点にあります。民法第606条には、賃貸人は賃借人に物件を使用収益させるために必要な修繕をする義務を負うことが明確に定められています。給湯器は、賃貸住宅で生活する上で不可欠な主要設備です。そのため、入居者の故意・過失によらない経年劣化による故障の場合は、貸主(大家)が修繕費用を負担するのが原則的な法解釈です。
給湯器の一般的な耐用年数は10年〜15年です。この耐用年数を超過した上での故障は、入居者が適切に使用していた限り、経年劣化と見なされます。この場合、入居者が負担すべきは、日常的な清掃や部品交換などの「小修繕」に留まります。例えば、入居から数年で給湯器が故障し、契約書に「一切の修繕費用は入居者負担」とあっても、貸主に「故障の原因は経年劣化であり、これは民法606条に基づき貸主の修繕義務の範囲内です」と通知することが非常に有効です。判例においても、エアコンや給湯器といった主要な生活設備の修繕費用を賃借人に負担させる特約は、特約の存在を認識させ、賃借人に不利にならない程度の対価補償がない限り無効と判断されています。まずは内容証明郵便で貸主に修繕義務の履行を求めましょう。
詳しく知りたい方はこの記事もご覧ください。

賃貸契約における給湯器の交換費用の負担の原則は、あくまで「貸主負担」です。契約内容を鵜呑みにせず、民法の修繕義務規定を根拠として主張することで、不当な費用請求を退けることが可能となります。交渉を有利に進めるためには、費用の交渉よりも先に「給湯器が故障した事実」のみを伝え、大家側から専門業者を手配させる流れを作ることが最善の戦略です。

お問い合わせ(24時間365日)
電話・フォームで即手配
管理組合が「PS設置の後継機種を認めない」時の最終交渉術
管理組合は建物の景観維持や安全性を理由に、後継機種への交換を拒否するケースが多く発生します。交渉を成功させるには、規約を遵守しつつ、既存品との違いをデータで示した具体的な申請資料を用意することが不可欠です。総会を待てない緊急時には、理事長権限での承認を得る「裏ルート」を活用することで最短での交換を目指します。
分譲マンションでPS設置型の給湯器交換を進める際、管理組合の承認は避けて通れない最大の難関です。機器の老朽化が進み、緊急で交換が必要な状況であっても、既存機種と異なるサイズや、省エネ型のエコジョーズへの切り替えは、共用部分である排気口の位置やPS扉の加工に関わるため、承認が遅れたり、最悪の場合は拒否されることがあります。管理組合は、建物の景観維持や、排気による居住者の安全性確保を理由に、交換機種の選定に厳しい制限を設けることが一般的です。しかし、給湯器の故障は日常生活に直結する問題であり、安全性の確保と生活上の必要性を訴え、合理的な根拠に基づいた交渉で承認を勝ち取らなければなりません。交渉をスムーズに進め、交換費用の負担だけでなく工期の遅れという二次的なリスクを避けるためにも、規約を遵守しつつ具体的な代替案と専門業者による安全性の証明を提示することが、迅速な解決の鍵となります。
「景観維持」の壁を突破する外壁色とサイズの申請資料見本
管理組合が交換を認めない最大の理由は、新機種導入による景観の不統一です。この壁を突破するためには、規約で定められた外壁色やサイズ基準を細かく分析し、その基準を厳守した上での具体的な申請資料を作成することが必須です。規約の「外観の変更禁止」条項では、色調や材質、PS扉の意匠変更を禁止していることがほとんどです。新機種に交換する際、特にエコジョーズなどはドレン排水処理の経路確保が必要になり、共用部分への影響が避けられない場合があります。この共用部分の改変リスクを、申請の段階でいかにゼロに近づけて説明できるかが、承認の分かれ道となります。
景観維持という懸念を解消するための具体的な申請資料には、以下の要素を必ず含めてください。
- 現行のPS扉の色を専門業者に計測させ、新機種のPS扉カバーを特注色で近似色に塗装することを提案する資料。
- 交換機種メーカーから入手した、現行機種と新機種のサイズを重ね合わせた図面(オーバーレイ図)。この図面で排気口の位置が変更されないことや、寸法差が規約の許容範囲内であることを明確に示します。
- 省エネ型エコジョーズへの交換の場合は、ドレン排水処理が規約違反にならないよう、専門業者と相談し、適切に処理できる計画(例:ドレンアップ工事など)を申請書に明記します。
景観維持を重視する管理組合に対しては、「新機種は排気効率が向上しているため、居住者の安全性が高まる」という機能面でのメリットも同時に訴えるべきです。見た目を維持し、安全性を高めるという論理は、管理組合の承認を得やすい交渉材料になります。特注塗装の費用は交換費用に追加されますが、管理組合の懸念を払拭し、交換を迅速に進めるための必要経費として計上すべきです。単なるカタログ情報ではなく、規約に基づいた詳細な技術情報を提示することで、交換の合理性を管理組合に示すことができます。

景観と安全性の両面から管理組合の懸念を解消する資料こそが、承認への最短ルートです。単なるカタログ情報ではなく、規約に基づいた詳細な技術情報を提示することで、交換の合理性を管理組合に示すことができます。
総会を待たずに交換承認を勝ち取る理事長への裏ルート
給湯器の故障は生活に直結する緊急性の高いトラブルであるため、総会を待つ必要は原則としてありません。承認を迅速に得るためには、管理組合のトップである理事長や、設備担当理事への直接交渉が最も効果的な裏ルートとなります。総会は年に一度程度しか開催されず、その決定を待っていたのでは、お湯のない生活を何ヶ月も強いられることになり、これは現実的ではありません。多くの管理規約には、緊急時の対応に関する条項が設けられており、理事長や管理会社に一定の権限が付与されています。この緊急時の権限発動を促すためには、客観的な証拠を用いて「緊急事態」であることを証明する必要があります。
緊急時の理事長へのアプローチは以下の手順を踏むことで成功率が向上します。
- 給湯器のエラーコードと製造年を正確に伝え、経年劣化による修理不能、または部品供給終了を明確に伝えます。
- 専門業者による**「修理不可証明書」を取得し、交換の必要性が「緊急事態」であることを書類で証明します。
- 理事長に対し、承認が遅れることによる居住者の生命・健康への影響(冬場の入浴困難による健康リスクなど)を具体的に訴えます。
この際、理事長が個人的な責任を負わないよう配慮することが、交渉のポイントです。例えば、「この機種は既存品と同等品として、次回の理事会で事後承認とする」という特例的な承認の形を提案します。具体的な交渉事例として、給湯器が完全に停止した場合、理事長権限で承認を得て先に工事を行い、費用については仮払いとして後日理事会で正式承認を得るという手法が実際に用いられています。この手法を用いるためには、交換機種の仕様を既存品と極力一致させ、理事長がリスクを負わないための合理的な手続き案を提示することが重要です。

緊急性を証明する客観的な資料と、理事長がリスクを負わないための合理的な手続き案を提示することで、総会決議を回避し、最短で交換費用の承認を勝ち取ることができます。
賃貸で費用負担を完全に回避する大家への「初動連絡」の裏ワザ
賃貸物件で交換費用の負担を避けるには、大家への「初動連絡」が最も重要で、その後の交渉を左右します。給湯器が故障した事実は伝えるものの、「修理」や「交換」といった具体的な要求は避けてください。大家側が民法の修繕義務に基づき、故障原因の特定と業者手配の責任を負う流れを意図的に作りましょう。
賃貸マンションにお住まいで、給湯器が突然故障した場合、入居者が交換費用の負担を完全に回避できるかどうかは、大家や管理会社への最初の連絡方法にかかっています。多くの人がやってしまいがちな失敗は、すぐに「給湯器が壊れたので交換してください」と具体的に要求することです。この伝え方をしてしまうと、貸主側から「使用方法が悪かったのではないか」「なぜ勝手に交換が必要だと判断したのか」といった論争の余地を与えてしまい、費用負担の議論に巻き込まれることになります。費用負担を回避するための裏ワザは、給湯器の「修理」や「交換」という言葉を一切使わず、客観的な「状況報告」に徹することです。貸主は民法上の修繕義務を負っているため、まずは賃貸住宅の設備が機能しなくなった事実のみを伝えることに注力すべきです。これにより、入居者が主体的に動くことなく、貸主側の責任で故障原因の特定と業者の手配をさせる流れを自動的に作ることができます。
「エラーコードのみ」を伝えることで責任を放棄できる理由
大家への初動連絡では、具体的な「修理・交換」の要望を避け、「エラーコード」と「現状」のみを伝えることで、入居者側の責任を放棄できます。これが費用負担を回避するための最も有効なテクニックです。エラーコード(例:「140」「E-911」)は、機器のどこに問題があるかを示す技術的な情報であり、入居者がそれを修理すべきか、交換すべきかという法的判断をする必要がないからです。入居者が勝手に「交換が必要」と判断して業者を手配した場合、その業者選定や工事内容の妥当性について大家から追及を受けるリスクが生じます。
一方、「エラーコードE-140が表示されてお湯が出なくなりました」とだけ伝えれば、大家は修繕義務に基づき、そのエラーコードを解決するための専門業者を手配する責任を負います。入居者側はあくまで「使用できない事実」を伝えただけ、という立場を堅持できるのです。具体的な連絡例として、大家または管理会社へのメールやチャットで「本日15:00頃、給湯器のリモコンにエラーコードXXXが表示され、お湯が全く使えなくなりました。ご確認をお願いします」と、事実のみを淡々と記述します。この連絡を入れた時点で、民法上の修繕義務履行の「催告」が完了します。

もし大家が迅速に対応しない場合は、入居者が業者を手配し、その費用を大家に請求(求償)することが可能となりますが、まずは大家に責任を持って対応させる流れを優先すべきです。これにより、入居者が交換費用を立て替えるという一時的な負担も回避できます。「修理」「交換」といった言葉を一切使わないことで、業者選定の権限を大家側に留め、入居者側は費用負担のリスクを負うことなく、問題解決のイニシアチブを貸主側に移すことが可能です。
勝手に業者を手配した人が必ず支払うことになる追加費用
賃貸物件で故障時に大家に無断で業者を手配した場合、その修理・交換費用は全額自己負担となるリスクが極めて高くなります**。これは、入居者が費用を完全に回避するうえで絶対に避けるべき行動です。大家側には、自身が選定した業者、自身が指定した交換機種で修繕を行う選定権があります。大家の判断を無視して勝手に手配された業者の見積もり額が適正価格か、また交換された機種が物件の資産価値を損ねないか、といった判断を大家側で行うことができないため、費用請求を拒否されるのが一般的です。これは契約違反と見なされる可能性があります。
無断で業者を手配した人が負うことになる追加費用は、給湯器の本体価格だけにとどまりません。
- 大家が「不要不急の修繕」または「指定業者外」と判断した場合の全額請求。
- 大家指定の業者による再交換費用や違約金。
- 管理組合からの原状回復命令による再度の交換工事費用。
特に分譲マンションの賃貸物件の場合、PS設置型は共用部分であるため管理組合への申請が必須です。入居者が勝手に業者を呼び、この申請を怠った場合、管理組合から原状回復を命じられるという最悪のケースも想定されます。この場合の原状回復費用(再度の交換工事費を含む)は、すべて入居者の負担となり、交換費用(約15万円〜30万円)を遥かに上回る可能性があります。費用負担のリスクを負わないためには、大家が手配する業者の対応が遅い場合でも、「催促」に留めるべきです。

やむを得ず業者を手配する場合は、事前に大家から「業者選定と費用の立て替え」についての書面による許可を得ておくという原則を厳守することが非常に重要です。
管理組合と交換費用の判断ポイント
マンション給湯器の交換費用に関する問題は、「専有部分と共用部分の境界線」「契約上の修繕義務」「緊急時の管理組合承認プロセス」という3つの核心的な判断ポイントに集約されます。これらの要点を事前に理解し、適切な手順を踏むことが、金銭的・時間的なトラブルを回避する唯一の方法です。分譲マンションにお住まいの場合、給湯器本体は専有部分の設備であるため、交換費用は区分所有者(オーナー)の負担が原則です。
しかし、PS扉や排気口といった管理組合が管轄する共用部分に関わる変更を伴う場合は、事前申請が必須となります。この際、単に「壊れたから交換したい」と訴えるのではなく、景観維持への最大限の配慮と、新機種導入による安全性の向上という論理で交渉することが、承認を迅速に得るための決定的な要素となります。一方、賃貸マンションの場合は、給湯器の経年劣化による故障は、民法606条に定められた修繕義務に基づき、大家(貸主)が費用を負担する責任があります。
入居者が費用負担を完全に回避するための最善策は、故障の事実を**「エラーコードの表示」**という客観的な情報のみで伝える初動連絡に徹することです。これにより、大家側に業者を手配し、修繕の責任を負わせる流れを自動的に作ることができます。逆に、大家や管理組合の許可なく勝手に業者を手配する行為は、交換費用の全額負担や不必要な追加費用を招く最大のリスクとなります。給湯器の故障は緊急性の高い問題ですが、焦って自己判断で行動する前に、まずはご自身の立場における法的・規約的な責任の所在を明確にしてください。そして、本稿で解説した適切な交渉と連絡の順序を踏むことが、費用負担のリスクを回避し、最短で新しいお湯のある生活を取り戻すための最も実務的な行動指針となります。
よくある質問
- Q: 分譲マンションで給湯器本体が故障した場合、必ず全額自己負担ですか?A: 給湯器本体は専有部分であるため、原則として区分所有者(オーナー)の負担です。ただし、排気口やPS扉など共用部分の劣化が故障原因である場合、その修理費用は管理組合の負担となる可能性があります。
- Q: 賃貸で「入居者負担」と契約書にある場合、費用を拒否できますか?A: 拒否できる可能性が高いです。給湯器の経年劣化による故障は民法606条に基づき貸主の修繕義務となります。特約があっても、対価補償がない場合は無効と判断されるケースが多くあります。
- Q: PS設置型の交換で管理組合の承認が得られない場合、どうすれば良いですか?A: 新機種のPS扉カバーを特注色で塗装する提案や、新旧機種のサイズ比較図面を提出し、景観維持と安全性の両立を論理的に提示することで交渉します。
- Q: 大家への連絡で「エラーコードのみ」を伝える具体的なメリットは何ですか?A: 入居者が「交換が必要」という判断を避けることで、業者選定や費用の妥当性についての責任を放棄できます。これにより、大家側に修繕義務に基づいた業者手配を促すことが可能です。
- Q: 給湯器交換は総会を待たないと進められませんか?A: 給湯器故障は緊急性が高いため、総会を待つ必要はありません。専門業者による修理不可証明書を添え、理事長に特例としての承認(事後承認を前提)を求める裏ルートを活用することで、迅速な交換を目指します。
- Q: 勝手に業者を手配すると、どのような追加費用が発生しますか?A: 大家からの費用請求拒否に加え、管理組合からの原状回復命令(再度の交換工事費を含む)が発生するリスクがあり、給湯器の本体費用を遥かに上回る追加費用を自己負担することになります。
- Q: 分譲マンションでエコジョーズに交換する際の注意点は何ですか?A: エコジョーズはドレン排水処理が必要となるため、ドレン排水経路の確保方法が管理規約に抵触しないか、事前に専門業者と相談し、その計画を申請書に明記することが重要です。
参考情報
- 給湯器の交換に関する具体的な情報については、給湯器の交換をご覧ください。
- 交換にかかる費用の目安や、見積もり時に確認すべきポイントは、交換費用についてで詳しく解説しています。
- ガス機器設置のプロフェッショナルな情報については、一般財団法人 日本ガス機器検査協会のサイトを参照してください。